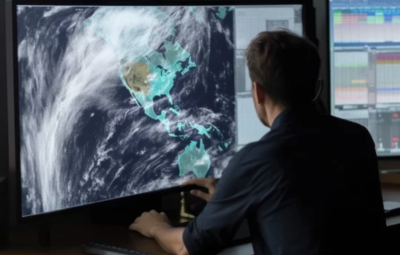筆者・志村 朋哉
広告
南カリフォルニアを拠点に活動する日米バイリンガルジャーナリスト。オレンジ・カウンティ・レジスターなど、米地方紙に10年間勤務し、政治・経済からスポーツまで幅広く取材。大谷翔平のメジャー移籍後は、米メディアで唯一の大谷番記者を務めた。現在はフリーとして、日本メディアへの寄稿やテレビ出演を行い、深い分析とわかりやすい解説でアメリカの実情を日本に伝える。
通信037
サーフィンの光と影
南カリフォルニアの“波の文化”を学ぼう
南カリフォルニアの夏といえば、やっぱりビーチです。海岸沿いの駐車場は朝から満車。サーフボードを抱えた若者たち、海水浴にやってきた家族連れ、日焼けを楽しむ観光客。とにかく人でごった返します。
そんな中、ひときわ目立つのがサーファーたちの存在です。それもそのはず。サーフィン文化は、いまや南カリフォルニアを象徴する存在です。
「多くの人がカリフォルニアに移住する動機のひとつが、サーフィンです。トッププロから初心者まで、皆“あの波”に憧れてやってくるんです」と語るのは、地元紙オレンジ・カウンティ・レジスターで「ビーチ担当」を務めるレイラン・コネリー記者。
今回は、そんな南カリフォルニアの“サーフカルチャー”を少し掘り下げてみましょう。
サーフィンの起源
サーフィンのルーツはハワイ。王族たちが波に乗っていたという記録もある伝統文化です。それが20世紀初頭、カリフォルニアにも伝わりました。
「1920年代ごろ、ハワイ出身のデューク・カハナモクやジョージ・フリースらが、初めてこの地域に波乗り文化を持ち込みました。そこから少しずつ、カリフォルニアの海岸に“波に乗る人たち”が現れるようになったんです」(コネリー)
当時はまだ板も大きくて重く、ウェットスーツもありません。寒さや波の激しさを乗り越える、いわば“男の冒険”だったともいえます。
“カルチャー”としての広がり
サーフィンが一気に市民権を得たのは、1950〜60年代。まず技術的な進歩によって、サーフボードは軽く扱いやすくなりました。そして映画『ギジェット』や『エンドレス・サマー』が公開され、サーフィンは一躍“自由と青春の象徴”に。
そしてこの時代、サーフスタイルを広めたのがアパレルブランドです。例えばクイックシルバーは、1970年代にオーストラリアから南カリフォルニアへ進出し、ニューポートビーチでボブ・マクナイトとジェフ・ハックマンによって「クイックシルバーUSA」がスタートしました。
“自由でラフなビーチスタイル”は、Tシャツやサンダルといった日常着に溶け込み、世界中のファッションにも影響を与えるようになったのです。
いまや南カリフォルニアでは、サーフィンは単なる趣味ではなく“生活の一部”です。「この地域では、朝サーフィンしてから出勤するのが日常。ジム代わりに波に乗る人も多いですし、中学や高校で“サーフィンクラス”がある学校もあります」とコネリー記者。
華やかさの裏にある課題
とはいえ課題もあります。
サーフィンには、波の優先権や安全確認といった基本的なルールがあります。人気スポットでは、「このビーチは自分たちの場所」という“縄張り意識”が根強く残っていて、「初心者や観光客が知らずにルールを破ると、トラブルになるケースもある」とコネリー記者は言います。
生活コストの問題も深刻です。海沿いの住宅費は南カリフォルニアでも特に高く、多くのサーファーが内陸部から車で1時間以上かけて通う生活を送っています。
そして近年注目されているのが、プラスチックごみの増加などの環境問題です。サーフィンが“自然との共生”である以上、サーファーたちが環境保護に積極的なのは当然の流れかもしれません。実際、彼らは定期的に浜辺のごみ拾いや、水質チェック、野生動物の保護活動などに取り組んでいます。
あなたの“波”を探しに
サーフィンとは、ただ波に乗るスポーツではなく、自分と向き合う時間であり、自然とのつながりを感じるライフスタイルです。
「波に乗る瞬間の“高揚感”。これはサーファー同士をつなぐ、言葉を超えた共通体験なんです」とコネリー記者。
せっかくこの地に暮らしているのですから、一度、その波に乗ってみませんか?皆さんの中の何かが変わるかもしれません。
(7/17/2025)
あわせて読みたい
ピックアップ
最新の記事
- 【~Jan 29】Mitsuwa Market Place 今週のお得商品!
- カイザー・パーマネンテ医療従事者数千人が新たな労働協...
- ビッグベアのワシのカップル、今シーズン初の産卵 今年...
- Tokyo Central Emeryville店 1月31日グランドオープン!...
- フラトンで男性が死亡しているのが発見 捜査が進行中(...
- LAXにも影響 全米で大規模な冬の嵐 航空網に深刻な混...
- 1/26~2/1📱魔女ともえの携帯番号運氣UPアドバイス
- KYOTO MARUHISA 刺し子コースターづくりワークショップ
- JINSアボット・キニー店 1周年記念イベント開催
- メトロ理事会がサウスベイ交通計画を承認、ホーソーン大...