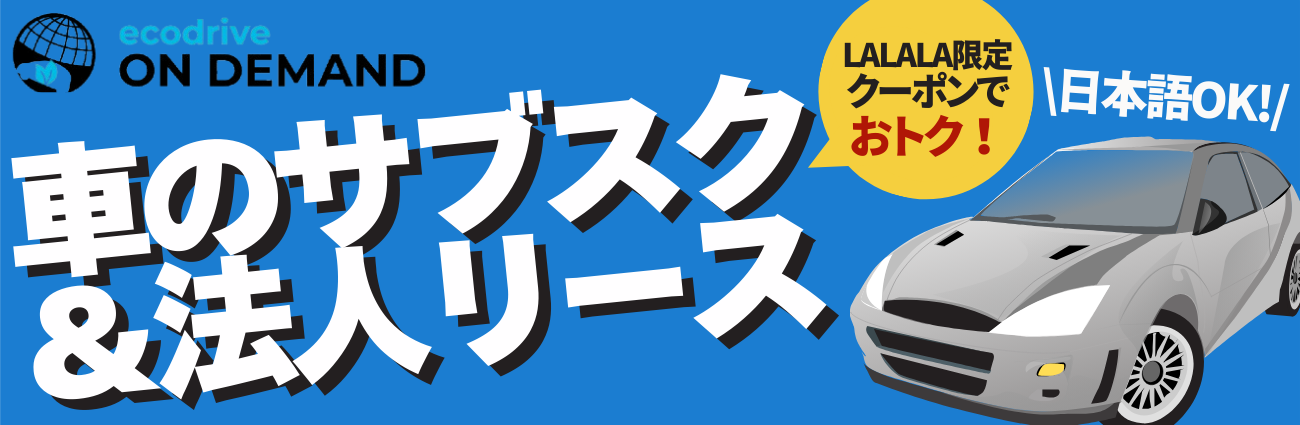筆者・志村 朋哉
広告
南カリフォルニアを拠点に活動する日米バイリンガルジャーナリスト。オレンジ・カウンティ・レジスターなど、米地方紙に10年間勤務し、政治・経済からスポーツまで幅広く取材。大谷翔平のメジャー移籍後は、米メディアで唯一の大谷番記者を務めた。現在はフリーとして、日本メディアへの寄稿やテレビ出演を行い、深い分析とわかりやすい解説でアメリカの実情を日本に伝える。
通信021
職場も巻き込む! March Madnessで
アメリカが熱狂する理由とは
今年もMarch Madness(3月の狂乱)の季節がやってきました。大学バスケットボールのナンバーワンを決める全米大会のニックネームです。皆さんの周りでも、スポーツ好きを中心に盛り上がっているかもしれません。試合は全米中継され、メジャーリーグのポストシーズンに引けをとらない視聴率を誇ります。日本人にはあまりなじみのない、この学生スポーツのイベントが、なぜアメリカでスポーツの枠を超えた人気を得ているのかを今回は解説します。
アメリカ版「甲子園」
まず、一度負けたら即敗退のトーナメント形式であることが大会を面白くしています。小規模で無名の大学が強豪チームを倒す「シンデレラ・ストーリー」も珍しくなく、それがさらにスリルを生み出します。この予測不可能な展開が、「March Madness」と呼ばれるゆえんです。
そこに「地元愛」と「母校愛」も加わります。人気プロスポーツチームがひしめく南カリフォルニアでは実感しづらいかもしれませんが、アメリカでは南部や中西部などを中心に、大学スポーツがプロスポーツと同じくらいの人気を誇り、多くの人が出身大学のチームを応援します。たとえ卒業生でなくても、地元の州や街の大学チームを応援するのが当たり前です。ロサンゼルスでも、UCLAやUSC(南カリフォルニア大学)の服を着た人をあちこちで見かけますよね。夏になると、日本各地で甲子園に出場する「おらが街の学校」を応援して盛り上がるのに近いといえます。
もう一つ、March Madnessの人気に拍車をかけたのがoffice poolの広まりです。これは職場の同僚が集まり、bracketと呼ばれるトーナメントの勝敗予想表を作成し、誰が最も的中させるかを競うゲームです。番狂せが頻発するため、大学やマスコットの好き嫌いなどをもとに適当に選んだ予想が大当たりすることもあり、普段スポーツを観ない人まで巻き込んで盛り上がります。
楽しむポイント
せっかくなので、March Madnessの熱狂に参加したいという人は、まずは応援する大学を選んでみましょう。出身校や思い入れのある大学がないのであれば、地元ロサンゼルスから出場しているUCLAを応援するのもいいかもしれません。今大会は第7シードで、20日の一回戦でユタ州立大学(10シード)と対戦します。同じく南カリフォルニアのUCサンディエゴ(12シード)は、ミシガン大学(5シード)とぶつかります。
近年は同時期に開催される女子のトーナメントも人気が上がってきています。こちらは地元UCLAとUSCがともに第1シードに選ばれていて、優勝候補と目されています。USCでは、大学最高選手との呼び声も高い2年生のジュジュ・ワトキンズが注目を集めています。
これから4月7日の男子決勝戦まで、試合のある日は、バーやレストランで中継が流され続けるはずです。応援するチームのグッズを身につけて観戦に行っても楽しいかもしれません。ぜひアメリカの大学スポーツ文化に触れながら、March Madnessの熱狂を肌で感じてみてください。
(3/21/2025)