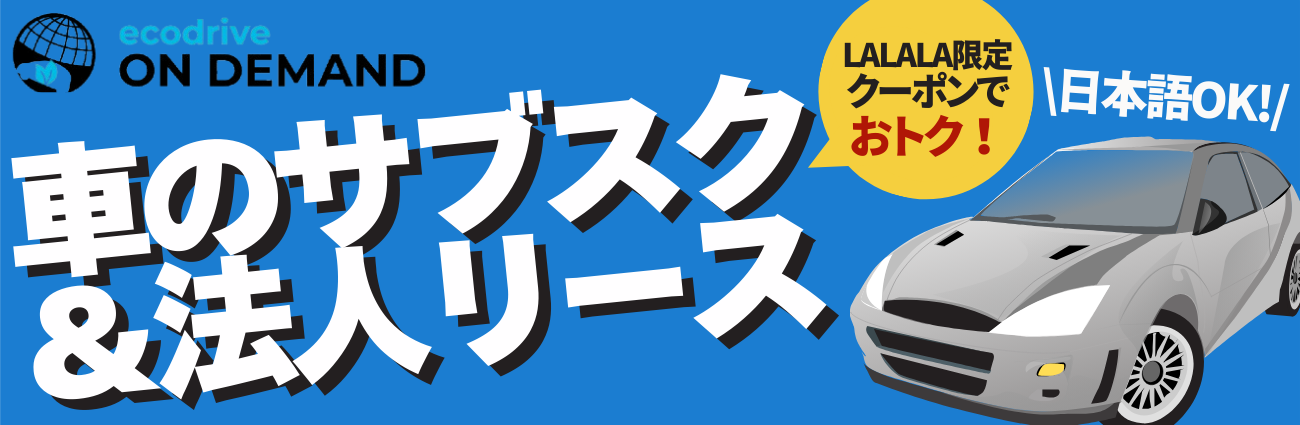広告

第二十四回
日本料理のマナー
「手皿」はしてはいけません
先週号に引き続き、「日本料理のマナー」について確認して参りましょう。
会食をしていますと、意外と器を引きずる人が多いことに気づきます。器も机も傷つける上、不快な物音がたってしまいます。おもてなしの一環である大切な器を丁寧に扱うことは食す側の重要な心得。器を傷つけない配慮として、引き寄せる時は引きずらず、少し持ち上げるようにします。
食後の器を重ねることも控えましょう。
また、器の蓋は元通りに戻します。時々、蓋を裏返しにしたり、ずらして器に戻す方がいらっしゃいますが、そのマナーは間違いです。そのようなことをすると、食器が欠けたり、割れてしまうことがあります。器の蓋は元通りに戻しましょう。
料理を口に運ぶ時に、手を受け皿にして添える「手皿」はしてはいけせん。器を持ち上げるか、小皿や器の蓋、もしくは懐紙を受け皿にします。
日頃からお持ちになると便利な和小物として「懐紙」をお勧めしています。
懐紙はその名の通り、懐に入れて携帯する紙の束のことで、平安時代から使われている日本の伝統文化です。今は主に茶席でお菓子をいただく時の取り皿として使いますが、元々は、和歌を懐紙に書いて詠む、物を清めるなど、使い方は様々でした。特に食事席に懐紙をお持ちになると、とても重宝します。魚の骨などを口から出す時の口元、お皿の一所に寄せた食べ残し、使った後の箸先など、人に見せたくないものを懐紙があれば隠すことができます。また、両手で食すフォーク・ナイフと違い、箸は片手なので、焼き魚の身が骨からはずれない時など、食べ物をもう片方の手で押さえたい時があります。焼き魚の頭の部分に四つ折り程度に畳んだ懐紙を置くと、手で押さえることができる上、とてもエレガントな所作となります。
口元や指先の汚れ、器やグラスについた口紅を拭くこともできます。ただし、食器を拭く時は、傷がつかないように、懐紙を揉み、柔らかくしてから使うと良いでしょう。

(5/22/2025)

筆者・森 日和
禮のこと教室 主宰 礼法講師
京都女子大学短期大学部卒業後、旅行会社他にてCEO秘書を務めながら、小笠原流礼法宗家本部関西支部に入門。小笠原総領家三十二世直門 源慎斎山本菱知氏に師事し、師範を取得する。2009年より秘書経験をいかし、マナー講師として活動を開始する。
2022年より、廃棄処分から着物を救う為、着物をアップサイクルし、サーキュラーエコノミー事業(資源活用)・外国への和文化発信にも取り組む。
https://www.iyanokoto.com